
日本の最北に位置するまち、北海道・稚内市に、創業から100年近く、地域の暮らしを支えてきたスーパーがあります。
このスーパーは単に商品を売る場所という枠を超え、「地域の食文化の担い手」であり、さらに人と人がつながるための「生活のインフラ」として大切な役割を担ってきました。
加えて、現在は店のイメージや価値を再構築する「リブランディング」にも取り組んでいます。 これは変革の場として、「日本最北端の稚内という北のはしから、未来のあたりまえ」をつくろうとする試みです。
今回は代表の福間加奈さんにインタビューさせていただき、ローカルスーパーが果たすべき次の役割を紐解いていきます。
まちの暮らしの拠点

相沢食料百貨店のはじまりは、曽祖父の代にまで遡ります。 創業当初は小売業からスタートし、その後は地域の小売店に卸す仲卸機能も担いながら、商いを広げていきました。
現在の店舗は、かつてデパートとして栄えていた建物であり、福間さんのお父様が買い取り、スーパーとして生まれ変わらせました。5階建てのビルの中には、エスカレーターの痕跡など当時の名残も残されています。 この地に深く根差し、人々の暮らしに溶け込む場として、相沢食料百貨店は今日も変わらず開かれています。
東京での出会いと、背中を押した言葉

福間さんが東京で就職したのは、国産ニットメーカーでした。 3年間勤務する中で大きな転機となったのが経営者が開催していた「思想講座」との出会いでした。 そこで学んだ、松陰先生や二宮尊徳の教えといった先人たちの知恵、そして社長からかけられた言葉が福間さんの胸に深く響き「地域を支える家業に、果たすべき使命がある」という強い思いに目��覚めたと語ります。
「社長が、勉強会を開いてくれたんです。二宮尊徳、吉田松陰。学校では教わらなかったような人物の言葉や思想を学んでいました。」
働き始めた当初、福間さんに家業を継ぐ気持ちは
なかったそうです。
しかし社長は、「家業があるなら継いだほうがいい」というメッセージを、福間さんに送り続けたそうです。
「はっきり言われたわけじゃないんですけど、そういうメッセージを何度もいただきました。」
講座で学んだ先人たちの思想、そして社長の言葉が、福間さんの心の中では、生まれ育った北海道の北のはしの町・稚内の現状と重なっていきました。
「地域が困っているのならば、自分だからこそ、やるべきことがあるのではないか。」
その思いを胸に覚悟を決めた福間さんは、Uターンを決意します。そして帰郷の際、社長が手渡したのはその心の象徴とも言える二宮尊徳像でした。
その像はいまも店の前に立ち、お店を見守っています。
事業承継のリアル

「家業を継いだ」と聞くと、まるで事前に用意されたバトンを自然に受け取ったかのように聞こえるかもしれません。
福間さんは違いました。自らの使命を自覚し飛び込み掴んだバトンです。
帰郷した2009年当時、お父様から「継いでほしい」という明確な言葉はなく、むしろ会社は売却も視野に入れていたほどでした。当然、社内に後継者を育てる体制や仕組みなどは整っていません。
決算書を開けば、「スーパーってこんなに儲からないの?」と血の気が引��くような数字が並んでいたそうで、その厳しい現実を前に、何から手をつければいいのか、糸口すら見えない中でのスタートでした。 家業を継いだばかりの頃は、組織的な歓迎も手厚いサポートもありません。
それでも、「創業100年まではやってみよう」という目標をまず決め、その覚悟を心の支えに足を止めることなく進み続けたそうです。
経済合理性では測れない、スーパーという「場」の力

相沢食料百貨店が徹底して守り続けてい��るサービスの一つに、稚内市内への「当日無料配達」があります。
このサービスには、利便性を超えた大切な意味があります。例えば、来店が難しい高齢者からの電話一本、あるいは葉書一枚の注文にも、スタッフが丁寧に対応します。
猛吹雪で外出さえ困難になるこの最北の町で、時には注文の品を届けるだけでなく、次の注文を「取りに」ご自宅まで伺うことさえあるといいます。
なぜ、そこまでするのでしょうか。
その背景には、福間さんの揺るぎない想いがあります。
「一人暮らしの方が、買い物や立ち話を通じて、社会とのつながりを感じられ�ること、それこそが健康寿命を支えている」という想いです。
だからこそ、相沢食料百貨店はただモノを売る場ではないのです。人がつながる「生活のインフラ」としてスーパーマーケットという「場」のあり方を常に見つめ直し、地域にとって絶対に必要な存在であり続けようとしています。
食を軸に、地域と協働する仕組みを


相沢食料百貨店は、大量生産・大量消費の流れの中で失われつつある「あたりまえの食」を日々の売場でていねいにつなぎ続けています。
「口に入るものだからこそ、誰がどう作っているのかにこだわりたい。その責任が、小売の立場にもあると思うんです」
と福間さんはおっしゃっていました。
その揺るぎない想いは、商品の販売だけではありません。
角打ちの開催や北のはし通信の作成など、スーパー以上の価値を、心を込めお客様へと届け�ていらっしゃいます。
顔の見える関係性と、ここにしかない豊かさ

「レジに立っていると、お客さんから差し入れをいただくことがあるんです。飲み物やお菓子など。『これ自分の分と一緒に買ったから、あなたも食べて』って」
この心温まるエピソードが象徴するように、お気に入り��のレジスタッフに会いに来る常連さんも多く、店は人と人との信頼と優しさで満ちあふれているそうです。
心の交流とはまた別の大切な側面があります。
冬の稚内は、猛吹雪で月に4〜5日も外出が困難になる日がある、日本で最も過酷な環境の一つです。そんな極限の状況でも「あそこに行けば食料がある」と地域の人が安心して暮らせる。
相沢食料百貨店は、人々の命を支える場所でもあり、「頼れる場所」としての役割も大切にされていると感じます。
人材との未来づくり
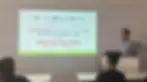
現在、店舗を支えるスタッフのほとんどは、地域の暮らしを知り尽くした地元の方々です。 今、福間さんが目指しているのは、スタッフ一人ひとりが「自分ごと」として主体的に意見を出し合える文化を育てること。
店舗や商品という目に見えるものを変えるだけでなく、組織の風土を変えていくことにも挑戦されています。
まとめ
相沢食料百貨店の福間さんの挑戦は、人口が減る一�方の地域に、場所という生活インフラを未来に残すという、あたたかくも地道な挑戦です。
地域食材を活かした商品の共同開発、リニューアルによる魅力的な「場」づくり、組織と地域との「共創」。
ひとりのお客さまの食卓を想い、地域の子どもたちに豊かな選択肢を残したいと願うこと。
大きな社会変化の波に対して「地域」という単位で応答しようとする希望を生み出していると感じます。
福間さん、ありがとうございました。
相沢食料百貨店EC:https://aizawa.official.ec/
HONE/亀元


.png)
.png)
.png)