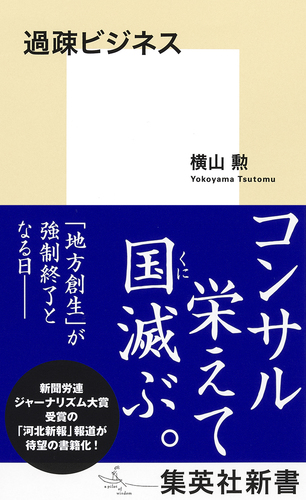『過疎ビジネス』地域が“喰われない”ための3つの心構え
- 桜井 貴斗

- 2025年8月11日
- 読了時間: 8分
更新日:2025年11月9日

集英社新書から出版されている『過疎ビジネス』。
読み終えて強く思ったのは、地域が“食い物”にされないための条件は、誰よりも一次情報を取りに行き、制度の隙間に手を突っ込んで確かめ、自分なりの問いと答えを持ち続けることだということです。
河北新報社の調査報道が示したのは、「企業版ふるさと納税制度」が、運用次第で寄付と発注がからむ“還流”の構図を生みうる現実(本書/関連報道)。制度は最大で寄付額の約9割が税軽減される設計だからこそ、適切なガバナンスが不可欠になります。
本記事では桜井が直接感じた「心構え」と「原則」を言語化し、地域の現場で実装できる言葉として残すべく、記事を書いてみました。
目次
①自ら一次情報をとりに行く
②制度の穴は“自分ごと”で塞ぐ
③自分の問いと答えを持つ
(書籍説明)
コンサル栄えて、国滅ぶ――。
福島県のある町で、「企業版ふるさと納税」を財源に不可解な事業が始まろうとしていた。
著者の取材から浮かび上がったのは、過疎にあえぐ小さな自治体に近づき公金を食い物にする「過疎ビジネス」と、地域の重要施策を企業に丸投げし、問題が発生すると責任逃れに終始する「限界役場」の実態だった。
福島県国見町、宮城県亘理町、北海道むかわ町などへの取材をもとに、著者は「地方創生」の現実を突きつけていく。
本書は「新聞労連ジャーナリズム大賞」受賞の河北新報の調査報道をもとに、さらなる追加取材によって新たに構成した一冊。
桜井読後メモ:本書が突きつけた“地方創生”の現実
本書籍を読んで私が感じたのは強い憤りと使命感、そして巧妙に過疎ビジネスを行う小賢しいハイエナコンサルの「巧さ」でした。
企業版ふるさと納税とは、内閣総理大臣が認定した地域再生計画に位置付けられた事業に対して企業が寄附を行った場合に、損金算入措置に加え、法人関係税(法人住民税、法人事業税、法人税)に係る税額控除の措置が講じられている制度です。
令和2年度より、税の軽減効果は寄附額の最大約9割となっており、主に企業の節税対策と地域貢献に使われていたものでした。
しかし、この制度をうまく活用し、とある自治体に寄付した会社のグループ会社にその自治体が別案件として公募型プロポーザルという名目で仕事を発注していたことから物語は始まります。
寄附を行う法人に対し、寄附を行うことの代償として以下の行為が禁止されています。
寄附を行うことの代償として、補助金を交付すること
寄附を行うことの代償として、他の法人に対する金利よりも低い金利で貸付金を貸し付けること
寄附を行うことの代償として、入札及び許認可において便宜の供与を行うこと。
福島県国見町×ワンテーブル社×ベルリング社の“疑惑の救急車”が示したもの
実態の詳細は本書に譲りたいため、ここでは簡単に実際に起こった2つの不可解な関係をまとめてみます。
福島県国見町が寄付を原資に高規格救急車12台のリース事業を進めた案件では、議会側が「特定企業に有利な仕様」等を疑問視。寄付元と受注・製造側のグループ関係が指摘され、調査が拡大しました。
2024年11月22日、内閣府は「契約手続きの公正性等に問題」「便宜供与があった」として、同町の地域再生計画の認定を取り消しました。議会の百条委と町の第三者委で評価が分かれる局面も、制度運用への重い示唆であることがわかります。
福岡県吉富町×LOCAL2社×サードウェーブ社の“寄付=受託額”のレッドフラッグ
福岡県吉富町では、企業版ふるさと納税をサードウェーブが2022年7月末に550万円を寄付。同年11月の公募型プロポーザルで、LOCAL2が同額の550万円で受託した流れが、東洋経済の特集で問題提起されました。
町の議会資料でも、寄付企業名や受託先、参加1社だったことなどが確認できる。寄付と調達の独立、公告期間・評価の透明性などが問題視されています。“形式は公募”でも、こうしたレッドフラッグが地域各地で起こっています。
HONEのスタンス:地域が“喰われない”ための3つの心構え
企業版ふるさと納税、公募型プロポーザル、補助金・助成金を無くせばいいか?というとそういうものでもない。むしろ国からの交付金によって地域が支えられている面もあるため、援助がなくなってしまうことは地域の衰退に拍車をかけることになります。
では地域が喰われないためにどんな心構えが必要なのか。私自身感じたことをまとめてみたいと思います。
①自ら一次情報をとりに行く
私自身、1年間でおおよそ50を超える地域に足を運んでいます。
職業柄、リモートで仕事ができるとも言われていますが、自分の目・手足・頭を使って触れることで得られる情報がたくさんあります。
私は地域に行くと、その地域特有の場所(人気の観光スポット・美術館・博物館・ローカルチェーン・地元の美味しいお店)に足を運ぶようにしています。なぜなら、そういった場所にはその土地に根付いた文化を体現しているため、地域理解が深まるからです。

②制度の穴は“自分ごと”で塞ぐ
前述した通り、企業版ふるさと納税、公募型プロポーザル、補助金・助成金そのものが悪いわけではありません。これらの制度を悪用して儲けようとすることが悪いのです。
じゃあどうするか?ということで、自分たちが主体者・当事者になって進行しています。今期からまずは公募型プロポーザルに参加し、受託。自分たちの故郷は自分たちで守ろう、ということでコ・クリエーションスペースの運営を行っています。
悪用するような人を寄せ付けないためには自分たちがその人たちよりも自治体に信用されればいいだけの話です。まずは事業主体社となり、悪用されないように出張っていきます。
↓のようなイベントを行い、静岡市の創業支援・事業サポートを行っています。単なる応援・支援・伴走ではなく、利益に貢献するような取り組みを行う予定です。
③自分の問いと答えを持つ
①自ら一次情報をとりに行く、②制度の穴は“自分ごと”で塞ぐ、に近いですが、それらの活動をしていくと、「自分なりの答え」というものが見つかってくると思います。
どこかのお偉いさんが言っていた話ではなく、書籍やテレビの受け売りではなく、自分なりに解決すべき問いとその答えを持つことが大切だと思います。
自治体に迎合するのは簡単です。でもそれだけではうまくいきません。スタンスを持ち、時には意見を交わしながら進んでいくことが求められると思います。

【過疎ビジネスまとめ】地域を“消費地”にしない
観光戦略においても、文化経済戦略においても言えることですが、地域を消費させないための取り組みが今まさに求められていると感じました。
私が相対している先は過疎地域、離島、限界集落といった人口減少、少子高齢化、産業衰退の問題を抱えている場所です。だからこそ、一部地域は手当も手厚い。そうなると手当を目当てにした黒い影がチラついてきます。
お金を正しく使うために、そしてただ使うだけではなく後世に生きる使い方をするために、これからも消費されない地域づくりを目指していきたいと思います。『過疎ビジネス』は、強い憤り、強い使命感を持ち、働く燃料になりつつも、冷静さを保ちながら実務にあたっていきたいと思いました。
参考(一次情報・関連記事)
HONEについて
当社では、地方企業さまを中心に、マーケティング・ブランド戦略の伴走支援を行なっています。事業成長(ブランドづくり)と組織課題(ブランド成長をドライブするための土台づくり)の双方からお手伝いをしています。

大切にしている価値観は「現場に足を運ぶこと」です。土地の空気にふれ、人の声に耳を傾けることから始めるのが、私たちのやり方です。
学びや知恵は、ためらわずに分かち合います。自分の中だけで完結させず、誰かの力になるなら、惜しまず届けたいと思っています。
誰か一人の勝ちではなく、関わるすべての人にとって少しでも良い方向に向くべく、尽力します。地域の未来にとって、本当に意味のある選択をともに考え、かたちにしていきます。
\こ相談はこちらから/
その他、気軽にマーケティングの相談をしたい方のための「5万伴走プラン」もスタートしました。詳細はバナー先の記事をお読みください!
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
\こ相談はこちらから/
【記事を書いた人】

株式会社HONE
代表取締役 桜井貴斗
札幌生まれ、静岡育ち。 大学卒業後、大手求人メディア会社で営業ののち、同社の新規事業の立ち上げに携わる。 2021年独立。 クライアントのマーケティングやブランディングの支援、マーケターのためのコミュニティ運営に従事。