商品開発の“最短ループ”——地域資源を価値に変えるマーケティングリサーチとは?
- 2025年8月9日
- 読了時間: 8分
更新日:2025年8月11日
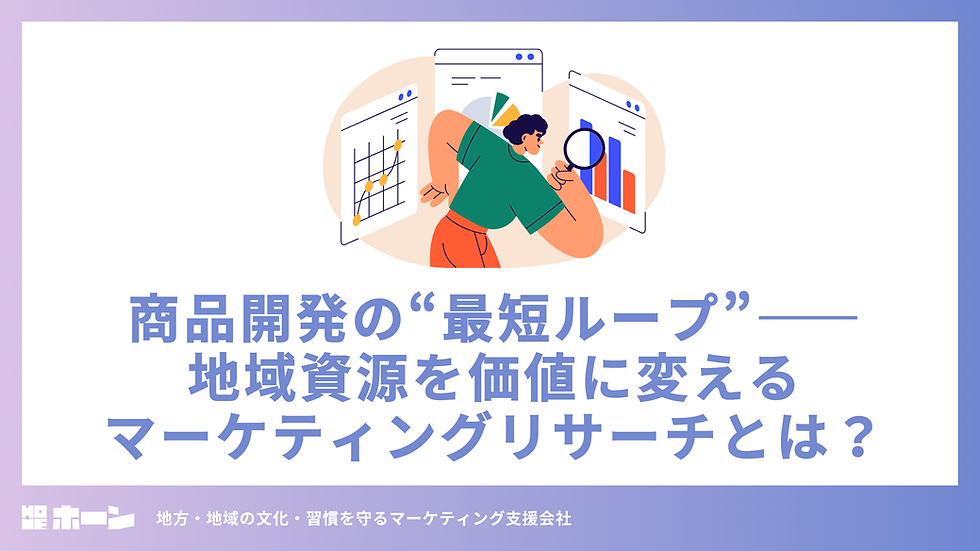
全国さまざまな地域のメーカーが、toB中心からtoCへ広げるときに失敗する理由は、“情報不足”ではなく決め方にあります。
HONEのマーケティングリサーチは、地域資源(GHIL)を主語に仮説を立て、およそ4週間で定性×定量→Small MVPまで回す“最短ループ”をご支援しています。
外部調査ツールや定性調査を使いつつ、現場感を持ちながら最終意思決定につなげていきます。本記事は、弊社の伴走支援と組み合わせた運用の全体像を、地域マーケティング/地方マーケティングの現場エッセンスを入れながらまとめてみました。
株式会社HONEでは過去のセミナー資料、お役立ち資料、会社紹介資料がダウンロードできます。
目次
意思決定から逆算して設計していく
地域資源(GHIL)を仮説の主語にしていく
4週間スプリントマーケティングリサーチで“答え”を出すには?
Day–7:現場観察から価値を発掘する
Day–14:定量調査設計→PSM(価格調査)→シーンを検証する
Day–30:Small MVPで現場の手応えを確かめていく
なぜ“スモールデータ”で商品開発が進むのか
地方で商品開発や新サービスをつくる際でも市場調査は必須ですが、ユーザー調査(定量・定性調査)をおざなりにしてしまうケースも散見されます。
実態としては費用が合わない、時間が足りない、専門的な人材がいない、と言った3つに集約されるようにも思いますが、私の場合、必ずしもきちんと時間とお金をかけて調査すればいいか?というとそうでもないと思っています(もちろん、時間とお金がかけられる環境にいるならそのほうがいいですが)。
ここでは最短で意思決定できるためのポイントをご紹介していきたいと思います。
意思決定から逆算して設計していく
商品開発の迷いは、調査の不足ではなく意思決定の不在から生まれます。
「とりあえず調査して事業がうまくいく先を調べよう」では良い結果は導き出せません。そもそもうまくいくとは何か?の定義をすることはもちろんですが、この考え方ではどの企業も「市場規模が大きそうで、競合がいなさそうな場所」に集中するため、特に地方企業の場合は大手のスケールメリットの前には太刀打ちできなくなります。
そのため、その事業に思い入れがあり、強い原体験があり、ちょっとのことではブレない芯がなければ迷いは払拭できないと考えています。
その上で、〈誰の・どんな状況に・何を・いくらで・どの導線で届けるか/やめるのは何か〉。このラインを先に作ってから、調査設問と検証手段(アンケート・観察・先行販売)を組んでいきます。
まずは意思決定から。これが迷いを断つ第一歩です。
地域資源(GHIL)を仮説の主語にしていく
GHILとは、地域を捉える4つの基本視点の頭文字です。
G:Geography(地理) 自然、地形、立地、交通など、地域の“場所性”
H:History(歴史) 地域が歩んできた歴史や文化、伝統
I:Industry(産業) 農業、製造業、観光業などの産業活動
L:Life(生活) 現代の人々の暮らしや地域社会の営み

「GHILフレーム」は、ビジネスにおける知見を「地域活性化マーケティング」に応用するという視点から研究されました。
特に、地域資源の発掘・整理・再構築という初期段階において、どのようなフレームワークが有効なのか。その選定と活用方法を示し、リサーチやディスカッションの現場で活用できる方法論として明確化することを目指しています。
具体的には、
地域資源をどのように整理・分類し、価値へと導出していくかというプロセスを体系化する
戦略立案やSTP・4Pなどの既存フレームと並ぶ、独自の“地域活性化向け思考ツール”を確立する
ワークショップやリサーチ、発想を促進する場で、実務的に活用できるよう整理する
を通じて、地域価値の創造を構造的に支援しようという試みです。
【あわせて読みたい】

4週間スプリントマーケティングリサーチで“答え”を出すには?
では、具体的にどんなフローで意思決定していけばいいのか?についても言及していきたいと思います。この章では4週間のスケジュールをざっくりと書いてみます。
厳密には企業によって個人差があるのですが、ここでは一般的な内容に留めておきます。もし気になる方は弊社までお気軽にご相談ください。
Day–7:現場観察から価値を発掘する
まずは現場を歩くこと。はじめはこれに尽きます。ネットや書籍での二次情報ではなく、自分の目と足で情報をとりにいくことを推奨しています。
下の画像は私たちが運営する民泊、ミクソロジーハウスふじやの近くにある漁協直営の海鮮屋さんで出てきた海鮮静岡おでん。
私たち地元民が普段食べている静岡の黒おでんと違い、海鮮の旨みがミックスされてとても美味しかったです!同じ静岡おでんでも海鮮丼屋のおでんは違うんだと発見になった事例です。
この体験からは、宿を訪れる方に向けておでんツアーを行ったり、お店によるおでん味比べを行ったりと、いろんな企画が思い浮かびました。

他にもあります。
↓は静岡市の工芸体験施設、駿府匠宿に訪れた際に手作り風鈴体験のサービスがありました。
お値段なんと、1つ3,000円から。ちなみにこの竹細工は駿河竹千筋細工といって、静岡市の伝統工芸の一つです(静岡・府中を流れる安倍川、その支流藁科川の流域は、昔からの良質の若竹、淡竹がとれたそうです。弥生時代の登呂遺跡から、ザルやカゴが出土され、この地では古くから竹製品が生活用具として定着していたことが伺われています)。
伝統工芸の手作り体験が3,000円でできて、さらに商品も持ち帰れるなんて、、こんな素敵なサービスを宿のプランに入れられたらいいなぁと感じました。

Day–14:定量調査設計→PSM(価格調査)→シーンを検証する
n1で自分の仮説をつくった後は定量調査を設計し、消費者調査を行います。
自分が考えた商品・サービスはどんな課題を持った消費者に届けるのが良いか?
現状、どのくらいの需要があるのか?
先行している競合他社はいるか?
どのくらいの価格帯で提供されているか?
などを調査設計し、価格調査にかけていきます。その上で、具体的な利用シーンをより精緻に仮設立てしていきます。
弊社のリサーチサービスの詳しい情報はこちらから。よりリサーチのことを知りたい、聞いてみたい方は直接お問い合わせいただけたらと思います。
Day–30:Small MVPで現場の手応えを確かめていく
MVP(Minimum Viable Product)とは、直訳すると最も小さく価値提供できるプロダクト。顧客及び消費者に価値を提供できる最小限のプロダクトのことを指します。
プロダクト・サービスの最終系を目指すのではなく、ターゲットが抱える課題を解決できる最低限の状態は何か?をつくることです。
先の静岡おでん・竹千筋細工の風鈴づくりを体験してほしいとして、いきなり立派なサイトや動画をつくるのではなく、まずはターゲットに実際に作ったプログラムを体験してもらう。そこでもらったフィードバックをもとにして改善をしていくイメージです。
以上のように〜7日まで現場をまわり、〜14日までに調査を行い、〜30日までにMVPをつくっていく。30日間をかけて骨子を作ることが可能だと思っています。
定性×定量を往復して“言葉”を磨く
30日間でMVPをつくった後は、商品・サービスを磨いて行きながら、定性調査(グループインタビューや単独でのデプスインタビューなど)を行い、ターゲットの理解を深めていくことが求められます。
大切なのは定量だけ、定性だけ、ではなく、論理と感覚の双方をバランスよく織り交ぜながら検証を行っていくことだと思います。
定量で深掘りしたい項目は定性インタビューで聞いてみる
定量調査で回答の多かったメッセージ、買いたいと考えている価格帯、どんなことに価値を感じたのか?などの回答は定性インタビューを行うことが効果的です。
長尺インタビューや座談会形式の雑談で深掘りをしていきます。ガッツリ対面でヒアリングするだけでなく、座談会などのリラックスした雰囲気で話を聞くと、思わぬコメントをもらえることもあります。
まとめ——“最適”を速く重ねていく
以上が商品開発の“最短ループ”——地域資源を価値に変えるマーケティングリサーチとは?でした。
大きな予算がなくても4週間で現場を見て、定量調査を行なって、最小限のプロダクト・サービスをつくることができると思っています。
地域マーケティング/地方マーケティング/商品開発の現場で効くのは、完璧ではなく“最適”な決め方です。いきなり決め打ちせず、フレキシブル事業を進めて行きましょう。
HONEのサービスについて
当社では、地方企業さまを中心に、マーケティング・ブランド戦略の伴走支援を行なっています。事業成長(ブランドづくり)と組織課題(ブランド成長をドライブするための土台づくり)の双方からお手伝いをしています。
私がこれまで会得してきた知識・経験を詰め込んだ「3つのサービスプラン」をご用意しており、お悩みや解決したい課題に合わせてサービスを組んでいます。ご興味のある方は、ご検討いただければと思います。
\こ相談はこちらから/
またサービスのリンク先はこちら↓
その他、気軽にマーケティングの相談をしたい方のための「5万伴走プラン」もスタートしました。詳細はバナー先の記事をお読みください!
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
【記事を書いた人】

株式会社HONE
代表取締役 桜井貴斗
札幌生まれ、静岡育ち。 大学卒業後、大手求人メディア会社で営業ののち、同社の新規事業の立ち上げに携わる。 2021年独立。 クライアントのマーケティングやブランディングの支援、マーケターのためのコミュニティ運営に従事。
※本記事は一部AIを活用して執筆しています。








