高価格帯商品はどう売れば良い?アンケート分析から導く、戦略的ターゲティングのヒント【マーケティング】
- 桜井 貴斗

- 6月17日
- 読了時間: 7分

今回は、高価格帯商品をどう売るか、そのターゲットをどう定めるかという実践的なマーケティング分析をご紹介します。
高価格帯商品が売れない理由は、高いから欲しい人が限られるのではなく、「誰にどんな価値で届けるか」が明確でない可能性があります。高価格だからこそ、データを使った仮説設計と分析が重要です。
本記事では、アンケート結果から得た仮説やインサイトについて紹介します。
株式会社HONEでは過去のセミナー資料、お役立ち資料、会社紹介資料がダウンロードできます。
高価格商品を売るなら、ターゲットの仮説設計から始める

価格以外の決定打はどこにあるのか、まず仮説を立ててみましょう。
たとえば、ボールペンを想像してみてください。大多数のユーザーは、1本のペンをすべての用途に使うと思います。しかし少数ながら「手紙は万年筆」「手帳には細字のゲルインク」「サインには油性ボールペン」と使い分けている層が存在します。最近ではガラスペンにも注目が集まっていますね。
こうした人たちは、筆記具に対するこだわりが強く、専門店やECサイトでレビューを読み込んだ上で購入している傾向があります。あるいは、特定のブランドへの愛着をもってリピートしているかもしれません。
ご支援の中で実施したアンケートでは、「複数のブランドを使い分けている人=その分野へのこだわりが強いのでは? 」「その分野へかける金額や購入場所によって、ターゲットが分かれるのでは?」という2つの仮説を立てました。
この仮説設計が、アンケート設計の土台になります。
仮説設計の具体的な流れを知りたい方は、こちらの記事をご参考にしてください。
▼合わせて読みたい🙌

「どこで買っているか」から見える、購買傾向の違い
次に注目したのが、購入チャネルごとの違いです。
例えば、とある消耗品のアンケート調査を実施した際に、大手ECプラットフォームで商品を購入している層と、リアル店舗(量販店)で購入している層を比較すると、明らかに前者の方が単価の高い商品を購入する傾向にありました。
この差は、単に「利便性」だけでなく、「自分の価値基準で商品を選びたい」という購買スタンスの違いが反映されていると読み取れます。
ご自身の商品が、ネット販売と、量販店(さらに言えば、コンビニ、大手スーパー、ドラッグストア、セレクトショップ、ブランドの直販店など)との差を数字で比較し、傾向の違いに仮説を立ててみましょう。
それぞれに傾向が見えてくるかもしれません。
高価格商品の価値は、日常ではなく“特別な時間”にある

もう一つ注目すべきは、「どんなときに使いたいか」という利用シーン。
これも、実際にアンケート調査を実施しています。
アンケートからは、「気分を切り替えるとき」「自分を労わりたいとき」「週末のご褒美」といった、リラックス目的で商品を使いたいという声が多く見られました。
この結果から、「日常的に使う商品」ではなく、「自分時間のスイッチとして使う特別な商品」としての価値づけが可能であると分かります。
データの交差点に仮説の答えがある
こうしたデータをクロス分析していくと、価格感と購買チャネル、商品の使い分け傾向の間に相関があることが分かってきます。
複数商品を使っている人は、比較的高価格帯の商品を選ぶ。
高価格帯商品を買う人ほど、ECチャネルを活用する。
意識の高いユーザーは、商品を“複数用途”で選び分けている。
これはあくまで、HONEが支援した事例における結果です。すべての高価格商品が当てはまるわけではありません。
今回は、商品が「高すぎて売れない」のではなく、「適切な文脈とタイミングで、適切な人に届いていない」ことこそが課題でした。その適切な文脈を見出すには、仮説設定と裏付けのアンケート調査が肝になるのです。
実践!アンケート設計のポイント

市場の中央値よりも高い価格設定をしている場合、金額以外の価値訴求と明確なターゲット設定が売上を左右します。
このターゲット設定を考える上で有効な手法が消費者アンケート調査です。
ただし、やみくもに質問を用意するだけでは、意味のある結果は得られません。「正しいアンケート設計」が必要です。
特にマーケティング戦略を考える上では、「業界内のユーザーの嗜好や行動」を捉えるためのカテゴリー内調査が役立ちます。
たとえば以下のような観点で質問を設計します
①カテゴリー商品・サービスの利用有無 | 利用しているか ※「利用している・利用していた・利用したことがない」といった項目で「既存・離反・未顧客」かをセグメントする ※必要に応じて「1年以内」や「半年以内」などの条件をつける |
②カテゴリー商品・サービスの利用頻度 | 利用している人限定。どの程度利用しているか |
③利用金額 | 利用している人限定。どの程度お金を使っているか |
④カテゴリー(業界)のイメージ | 記述式でキーワードを拾う |
⑤カテゴリー(業界)のブランド想起 | 思い浮かぶブランド名・商品・サービス名を選択式で回答してもらう |
⑥カテゴリー(業界)の利用ブランド | 現在使用しているブランド名・商品・サービス名を選択式で回答してもらう |
⑦ブランドの価値 | カテゴリーを利用したことがある人限定。商品・サービスにどんな価値があるかを複数選択or記述式で拾う |
回答を得られたら、分析しながら仮説を立て、施策を見極めていきます。
あわせて読みたい🙌

まとめ
アンケート調査は、仮説→設問設計→分析→再仮説化というプロセスを経ることで、より精度の高いマーケティング戦略の土台になります。ぜひ参考にしてください。
実際のマーケティングリサーチ支援の内容を公開中!
HONEではさまざまな商材の戦略立案を支援してきました。その一部を記事でご紹介しています。
あわせて読みたい🙌
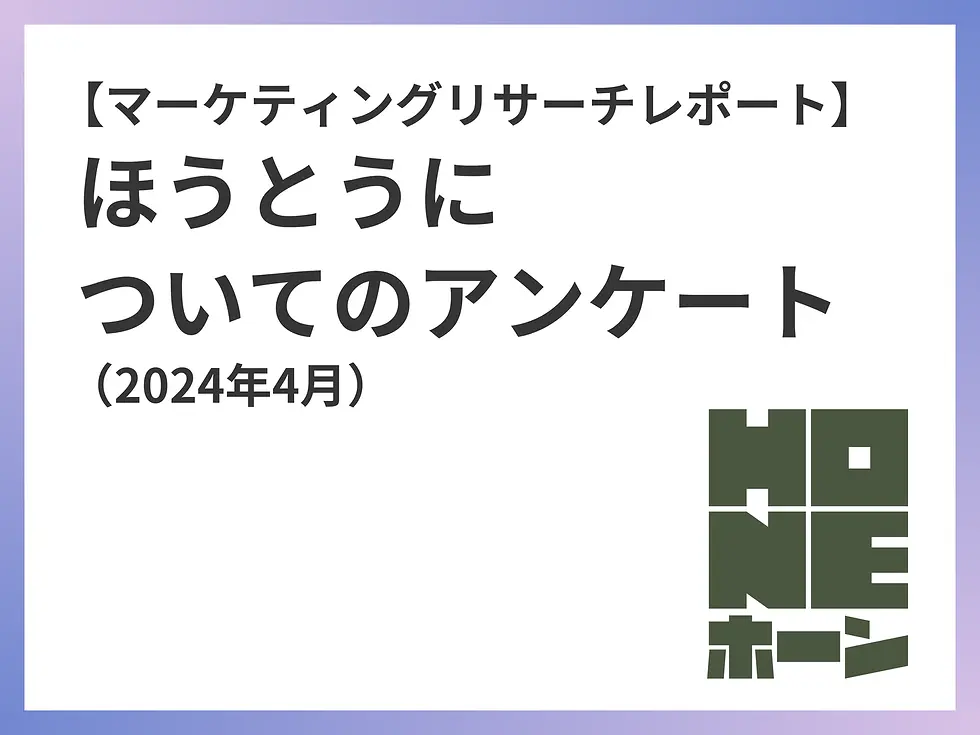
ほうとうは山梨県を代表する郷土料理で、小麦粉を練って作った平打ちの太麺を使った煮込みうどんのことです。
「ほうとうがこれから認知・販路拡大をしていくにはどのようなことが求められているのか?」「お土産としての「ほうとう」でどんなものだったら買いたくなるのか?」
マーケティングリサーチを行った際の内容を、記事やセミナー資料で公開しています。ぜひお役立てください。
セミナー資料のダウンロードはこちら
HONEのマーケティングサービスについて
当社では、地方企業さまを中心に、マーケティング・ブランド戦略の伴走支援を行なっています。事業成長(ブランドづくり)と組織課題(ブランド成長をドライブするための土台づくり)の双方からお手伝いをしています。
私がこれまで会得してきた知識・経験を詰め込んだ「3つのサービスプラン」をご用意しており、お悩みや解決したい課題に合わせてサービスを組んでいます。ご興味のある方は、ご検討いただければと思います。
またサービスのリンク先はこちら↓
その他、気軽にマーケティングの相談をしたい方のための「5万伴走プラン」もスタートしました。詳細はバナー先の記事をお読みください!
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
【記事を書いた人】

株式会社HONE
代表取締役 桜井貴斗
札幌生まれ、静岡育ち。 大学卒業後、大手求人メディア会社で営業ののち、同社の新規事業の立ち上げに携わる。 2021年独立。 クライアントのマーケティングやブランディングの支援、マーケターのためのコミュニティ運営に従事。
※本記事は一部AIを活用して執筆しています。








