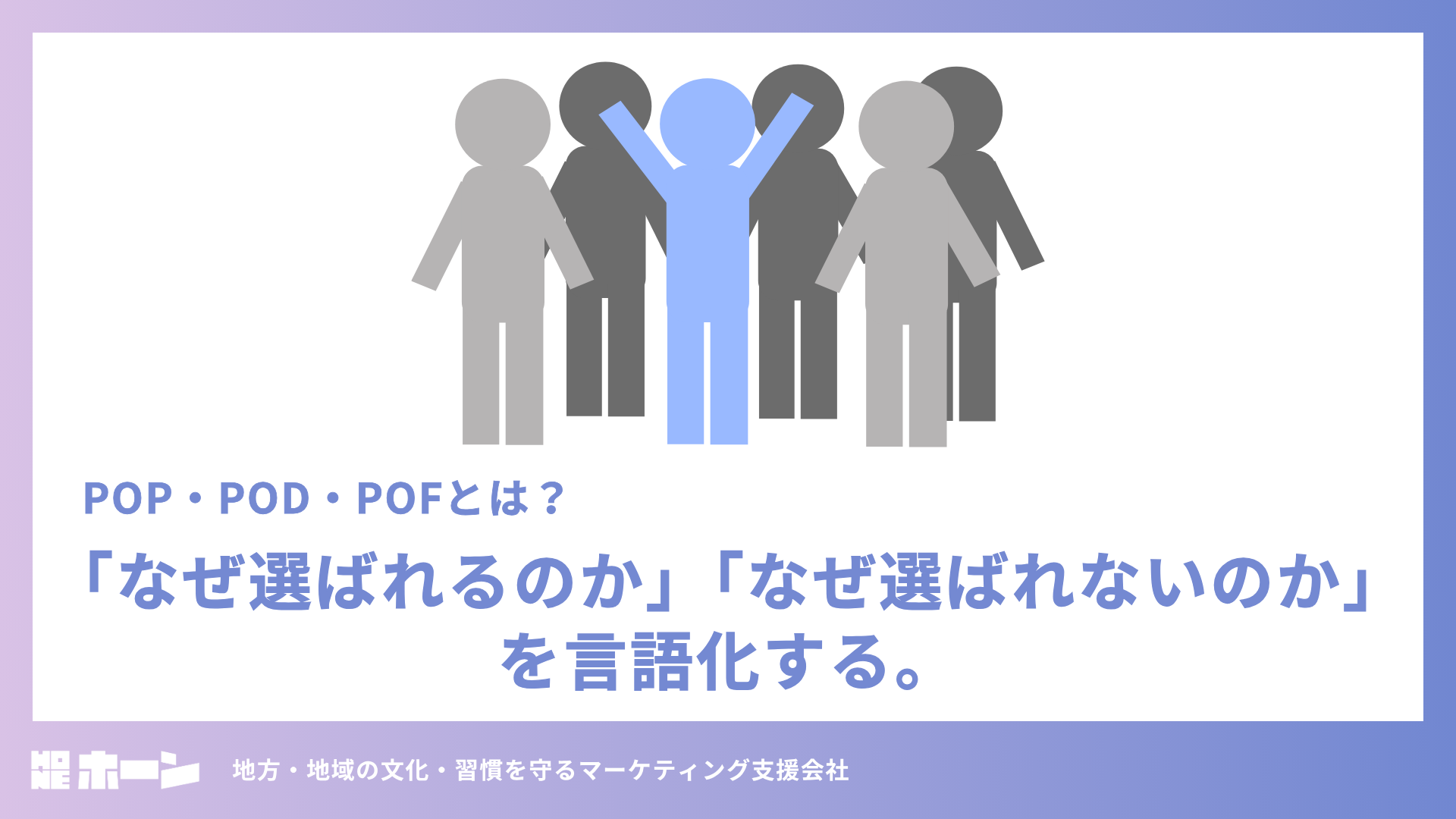『人がモノを買うしくみを言語化する』-"知ったかマーケター"からの脱却- を読んで。
- 桜井 貴斗
- 2025年11月24日
- 読了時間: 14分

日経BP社から出版されている『人がモノを買うしくみを言語化する』。
マーケティングとは、人に働きかけて、その人の心を動かす営みのこと。人の心の機序が理解できないと、その原理はわかりません。
一方で、多くのマーケティングの現場では色々なフレームワークに当てはめていくような作法が横行しており、そこまで遡った仕事ができていないことも多々あります。
本書では人間理解の本質に立ち返り、マーケターとしての矜持とはなにか?を問う1冊だと感じました。
本記事では桜井が心に残ったパートを一部抜粋してビジネスや生き方に転用できる点としてまとめてみました。
【人がモノを買うしくみを言語化する】書籍説明
トップマーケターが書き下ろした「マーケティングの解体新書」
30年以上にわたる実務経験で得た知見を1冊に集約
"ぐうの音も出ない"ほどマーケティングの神髄がわかる!
あなたは「マーケティング」を本当に理解していますか?
実は「知ったかぶり」かもしれません…。
ちょっとマーケティングかじると、とても賢くなった感じがします。でも、それを仕事に使ってみると、何か薄っぺらい感じから脱却できない。それは、フレームワークに踊っているから。もっと本当に腹落ちする形で理解しないと、実務の現場で「マーケティングできる」ようにはなりません。
では、「マーケティングが腹落ちする」とはどういうことでしょうか。その疑問に応えるべく、日本屈指のマーケターである著者が、長年にわたる実務経験の末にたどり着いた、"ぐうの音も出ない"ほどマーケティングについて理解できる考え方をまとめたのが本書です。
マーケティングとは、人に働きかけて、その人の心を動かす営みです。したがって人の心の機序が理解できないと、その原理はわかりません。一方で、多くのマーケティングの現場では色々なフレームワークに当てはめていくような作法が横行しており、そこまで遡った仕事ができていないこともしばしばです。これはマーケターに限らず、人ならば誰でも持っている「なんとか近道を探したい」という欲求から来ることでもあり、打破するのは容易ではありません。
また、ポジショニング・ブランド・インサイトなど、マーケティングにおいてその核となっている概念がいくつかありますが、なぜそれが重要か、その考え方をベースに仕事を組み立ていったらなぜ機能するのか、といったレベルで理解しているマーケターはほとんど存在せず、したがって現場での仕事は教条的になり、人の心まで遡ったやり方には、なかなかなりません。
そこで本書では、理論や概念先行だった多くのマーケティング解説本に対し、人の心の仕組みに遡って「人がモノを買うしくみ」を言語化し、マーケティングの重要なコンセプトと営みを解説していきます。それぞれのマーケティングコンセプトがそもそも何を意味しているのか、なぜなぜ人に有効に作用するのかを平易な言葉で説明した、いわばマーケティングコンセプトの解体と再構築によって、誰もがマーケティングについて腹落ちできるようにした、実務に即した「マーケティングの解体新書」とも呼べる一冊です。
(Amazonより)
著者について
富永 朋信(とみなが・とものぶ)
株式会社Preferred Networks エグゼクティブアドバイザー
早稲田大学卒業後、日本コカ・コーラなど9社でマーケティング業務に従事。うち、西友、ドミノ・ピザジャパン、Preferred Networksなど直近4社では最高マーケティング責任者を歴任。2025年7月、Preferred Networks エグゼクティブアドバイザーに就任。マーケティングの核=人間理解という考え方に基づき、企業におけるマーケティングの実践、ブランド戦略、コミュニケーション設計、人事研修の設計実施など多岐にわたるアドバイザリー業務を行う。政府系機関のオフィシャル広報アドバイザー(全世代型社会保障に関する広報の在り方会議 構成員、厚生労働省年金広報検討委員など)。日経クロストレンド アドバイザリーボード。日経COMEMOキーオピニオンリーダー。マーケターキャリア協会などマーケティング系団体・カンファレンスのアドバイザリーボード、議長などを多数歴任。著書に『「幸せ」をつかむ戦略』(日経BP、ダン・アリエリーとの共著)など。
人がモノを買う理由とは
(本書より) ●人がものを買う理由には、(1)なじみがあるから買う、(2)良いから買う。(3)好きだから買う、の3種類がある。 ●なじみをつくるためには、接触頻度を高めることにより、消費者の助成想起→非助成想起に入っていく必要がある。 ●良さをつくるための技術がポジショニングであり、それは競合/POP/PODを決め、実践していくことである。 ●競合は直感的に決めてはならない。ブランドの利用理由をベースにユースケースを網羅し、そのすべてについてポジショニングを設定し、ブランド戦略と照らし合わせた上でプライオリティを決めるべし。
マーケティングとは突き詰めると商売であり、商売の原理原則とは、(1)なじみがあるから買う、(2)良いから買う。(3)好きだから買うに収斂されていくのだろうと改めて感じました。
なじみをつくるにはまずは触れてもらい、「体験してもらうこと」であり、体験してもらうためにはフィジカルアベイラビリティー(※)を高めていくことが求められるのであろうと思います。
※フィジカルアベイラビリティとは、消費者が実際に商品を手に取りやすい、または購入しやすい環境を指す。具体的には、商品の配荷状況、パッケージデザイン・サイズ、店舗の棚などが含まれる。
詳しくは以下の記事で解説しています。
また「良いから買う」については他社よりも優れていることを認識してもらう必要があります。ここではマーケティング現場で役立つ整理考え方である、POP(Point of Parity)/POD(Point of Difference)/POF(Point of Failure)の意味を紐解き、ブランドや商品の“選ばれる構造”を知る必要もあると思いました。
POP(Point of Parity)/POD(Point of Difference)/POF(Point of Failure)については以下の記事で解説しています。
接触して認知してもらい、優位性を知ってもらって試しに使ってもらい、その後体験を通して好きになってもらうこと、が商売の大原則なんだと思います。
「すべてはターゲティングから」は、本当か?
(本書より) ターゲットの定義を「自ブランド名がサイネージに表記されている人」として、マーケティング施策を展開することはできるだろうか。少し考えればわかるように、これはもちろんできない。自ブランドがサイネージに表記されている人がどこにいるかわからないため、コミュニケーションの取りようがないからだ。 また、自ブランドがサイネージに表示されている、ということは、この人はすでに自ブランドを認知していることになる。だが、ブランドのことを知らなくても、そのブランドが提供できる価値や便益を知れば、欲しいと思ってくれる人も世の中には大勢いるはずだ。 つまりターゲティングとは、製品開発・コミュニケーションなどの対象を絞るため、自ブランドの商品・サービスを欲しいと感じている、またはそうなる可能性がある、コミュニケーション可能な人を定義することである。
上記の記載の通り、ターゲティングとは、製品開発・コミュニケーションなどの対象を絞るため、自ブランドの商品・サービスを欲しいと感じている、またはそうなる可能性がある、コミュニケーション可能な人を定義することとしています。
本書にも図解されていたターゲット概念を改めて書き起こしてみました。
ターゲットはコンセプトを体現する理想的な「コンセプチュアルターゲット」、理想なユーザーが所属する集団である「コミュニケーションターゲット」、みんなが買ってるから自分も買ってみようと考える「プロモーションターゲット」がいると定義されています。

ターゲットでよくやってしまいがちな失敗として、理想のユーザー設定が先行してしまうことでそんな人は実在しない、という事態に陥ってしまうことです。
かといって、誰にでも買って欲しいとターゲットを広げてしまい、曖昧なまま進んでしまうorターゲットが広すぎてリソース(時間・お金・人手)が足りない、ということにもなってしまってもいけません。
理想を掲げながらテストマーケティングを行いながら徐々に自分たちのブランドを好きになってくれている人にフォーカスしていく、という作業が求められると思っています。
ターゲティングは「人」より「意図」
(本書より) この経験を通じて、筆者は「人」の解像度ではなく、それよりも一段詳細なレベルである、その心にある「意図」を単位とした解像度でターゲティングをすべきである、という考えに至った。そしてこれを「人より意図」という駄じゃれめいた標語にしたためた。 本章ではスーパーマーケットの事例を用いたが、この概念はメーカー・小売りを問わず援用できると考えている。 例えば清涼飲料を例にとれば、コカ・コーラには、 ・止渇 ・気分を上げる ・好みの味を飲む ・糖分の補給 ・ブランドの持っている世界観(ブランドの世界観については、ブランドの章で詳しく解説する)への近接 などいくつもの利用理由がある。
ここではターゲティングを「人」ではなく、「意図(目的)」によって設定することを説いています。
意味合いとしてはカテゴリーエントリーポイント(CEP)に近い考え方だと感じました。
カテゴリーエントリーポイント(CEP)とは、新しい市場に参入する際や新商品・サービスを展開する際に、消費者の心に強く印象を残すための戦略的なアプローチを指します。
具体的には、消費者が「特定のカテゴリー(シーン)」を思い浮かべたときに、最初に頭に浮かぶブランドや商品・サービスを目指すこと、です。これにより、消費者の購買意欲を高め、行動変容に繋げていくことで競合他社との差別化を図ることができます。
カテゴリーエントリーポイント(CEP)の詳しい記事は以下にまとめています。
またコカ・コーラのターゲット・提供便益などをまとめたブランド価値規定をまとめると以下のようになります(本書より抜粋)。
項目 | 内容例 |
コンセプチュアルターゲット | 冒険心・好奇心の塊のようなティーン |
ブランドコンセプト | 気分を上げてくれるスイッチ |
機能的価値 | 炭酸・酸・カラメルの複合効果による刺激的な味 |
情緒的価値 | 若さを実感できること。それにつながる多くのシーンとの結びつき メインストリームであること 少し秘密めいていること |
パーソナリティ | メモラブルなシーンで必ず共にいてくれる伴侶 |
シンボル | ダイナミックリボン、ヒゲロゴ、赤色 |
Reason to believe | 100年以上にわたる歴史、世界一の清涼飲料であるという事実 |
※コカ・コーラを例にとったブランド価値規定の例(本書より)
コンセプチュアルターゲット、ブランドコンセプトが人ではなく「意図(目的)」となっているのがポイントだと思います。
ブランディングとは「人がものを認識する仕組み」のこと
(本書より) さて、ここまでで「人は概念を単位に認識する」という話から、概念とは何かについて論じてきたわけだが、ここで説明してきた概念と、本学前段で詳説したブランドは、ほぼ相似形をしていることに気づいた読者もいるだろう。 コーラに置き換えてみると、ブランディングという考え方・方法は、人がものを認識する仕組みをうまく援用する形で、自社商品やサービスの便益世界観などを構築するやり方であることがよくわかるのではないだろうか。人が参照点を恣意的に決定した上で、そこと比較する形で意思決定するからポジショニングが重要であるように、人は概念を単位に認識形成するから、ブランディングが重要なのだ。
ここでの概念とはブランドおよび商品に対して消費者が抱いているイメージであり、そのイメージの集合体が概念となり、コンセプトを形づけていくのだと思っています。
下の図は本書から抜粋したものですが、「コカ・コーラ」という概念のイメージを言語化したものです。コカ・コーラには「商品そのもの」「便益・価値」「意味」があり、それらのイメージの集合体がブランドのコンセプトとなると解釈しています。

こちらになぞって、自分たちが関わっているブランドを「商品そのもの」「便益・価値」「意味」それぞれで言語化してみようと思いました。そうすることでコンセプトにどんな言葉を置くのか?が見えてくるように思います。
インサイトは潜在的な購買理由のみが重要なのか?
(本書より) 自明さと一般性をマトリクスにしてみると、このように整理できる。 (1)自明さ:高✕一般性:高は、すでに一定の市場が確立しており、競争が激しいが手を抜けないゾーンである。 (2)自明さ:低✕一般性:高は、そこまでは顕在化していないが、成長性が高い、最も取りに行きたいゾーンである。 (3)自明さ:高✕一般性:低は、市場に知れ渡っているものの、共感してくれるオーディエンスが限定的なゾーンで、4象限の中で最もプライオリティが低い。 (4)自明さ:低✕一般性:低は、ニッチだが当たればその中のリーダーになることができるゾーンである。 これらのプライオリティは、その商品・サービスの市場におけるポジションによって違うが、一般的には規模に優れ、高いシェアを持っているブランドであれば、(1)→(2)→(4)→(3)、チャレンジャーであれば(2)→(1)→(4)→(3)または(2)→(4)→(1)→(3)といったところであろうか。 (中略) こうして整理してみると、マーケティング施策上着目する購買理由について、その自明さが高い方が優先度では劣るが、自明さが低ければよいというわけではない、ということがいえそうだ。自明だから大事ではない、自明でないから大事だ、ということはなく、すべての購買理由を包括的に理解することが大事なのだ。
インサイトとは消費者の潜在的な欲求と定義されることが多いですが、その潜在性が「自明な方が良いのか(または自明でない方が良いのか)」、「一般性が高い方が良いのか(またはニッチな方が良いのか)」というマトリクスで表現ができます。
下の図は本書から抜粋したものですが、「お酒を飲むインサイト」を自明・一般的で振り分けたものです。

筆者の富永さんも仰っている通り、一般的には規模に優れ、高いシェアを持っているブランドであれば、(1)→(2)→(4)→(3)、チャレンジャーであれば(2)→(1)→(4)→(3)または(2)→(4)→(1)→(3)となり、「自明さ:高✕一般性:高」、「自明さ:低✕一般性:高」が優先度として高いと定義されています。
自明さが高すぎると顕在ニーズになるし、自明が低くてもデビルインサイトと呼ばれるような「ネガティブなこと、コンプレックスなことを刺激するようなインサイト」を押しすぎてしまうと炎上につながってしまうリスクもあり得ると思うため、調整が必要だと感じました。
MVV&パーパスを浸透させるには「Routinizer (ルーティナイザー)」をつくること」
(本書より) 「決め事を社員の行動に変換する」ために、せっかく強い言葉、美しい言葉でミッションやバリューを決めても、社員の心に響き、残り、その行動に反映しなければ何の意味もない。そこで、ミッションやバリューに関わるトレーニングや意識づけのセッションを実施するのが正攻法だと思うが、筆者はもう一つ効率的かつ人の心の機序の観点から、合理的なやり方があると考えている。それは「Routinizer (ルーティナイザー)」をつくることである。Routinizerとは筆者の造語で、「何かを誰かのルーティンにするための仕組み」という意味である。
MVVやパーパスを規定したとしてもなかなか浸透しづらい、という声をよく聞きます。著者である富永さんは決め事を社員の行動に変換するにはRoutinizer (ルーティナイザー)」をつくること、を提案しています。 Routinizer (ルーティナイザー)とは「何かを誰かのルーティンにするための仕組み」と定義しています。
We are | We behave | 重要:We realize |
Mission Vision Purpose ブランド価値規定(ブランドパーソナリティを除く) | Value ブランド・パーソナリティ | 社員研修 うながし Routinizer(ルーティン化する) |
研修や評価制度、行動のルールなどを具体的に決めて実行するための仕組みまで落とし込むことが重要だと感じました。
MVVに関する記事は以下にて解説しています。
最後に・書籍情報
ここまでが『人がモノを買うしくみを言語化する』-"知ったかマーケター"からの脱却-の感想文でした。ここに書かれている内容は一部なのでご興味がある方はぜひ書籍を購入して読んでみてください。
HONEのサービスについて
当社では、地方企業さまを中心に、マーケティング・ブランド戦略の伴走支援を行なっています。事業成長(ブランドづくり)と組織課題(ブランド成長をドライブするための土台づくり)の双方からお手伝いをしています。

大切にしている価値観は「現場に足を運ぶこと」です。土地の空気にふれ、人の声に耳を傾けることから始めるのが、私たちのやり方です。
学びや知恵は、ためらわずに分かち合います。自分の中だけで完結させず、誰かの力になるなら、惜しまず届けたいと思っています。
誰か一人の勝ちではなく、関わるすべての人にとって少しでも良い方向に向くべく、尽力します。地域の未来にとって、本当に意味のある選択をともに考え、かたちにしていきます。
\こ相談はこちらから/
その他、気軽にマーケティングの相談をしたい方のための「5万伴走プラン」もスタートしました。詳細はバナー先の記事をお読みください!
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
\こ相談はこちらから/
【記事を書いた人】

株式会社HONE
代表取締役 桜井貴斗
札幌生まれ、静岡育ち。 大学卒業後、大手求人メディア会社で営業ののち、同社の新規事業の立ち上げに携わる。 2021年独立。 クライアントのマーケティングやブランディングの支援、マーケターのためのコミュニティ運営に従事。